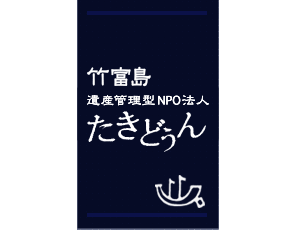民具づくり教室 2019/06/29
前回に参加できなかった生徒さん方の、�…

民具づくり教室 2019/06/8
今日の民具づくり教室は、藁を材料に箒を�…

第4回 にほんくらし籠
昨年の「第3回にほんくらし籠展」に引き続き、今年も竹富島から民具を出品しております。
今回は、月桃を素材とした民具を松竹さん、
トウヅルモドキを材料とした民具を狩俣さんが制作しました。
暮らしの中で受け継がれる、島の植物を使うくらしの道具。
人の手から生み出されるものには、温もりと力強さがあります。
この機会に、是非お立ち寄りください。
会期 2019年5月11日(日)−…

県立博物館新収蔵品展
4月30日からスタートしている、沖縄県立博物…
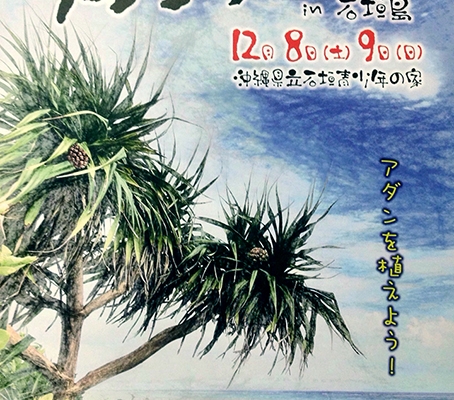
琉球弧アダンサミット2018
昨年の8月に池間島で開催された「琉球弧ア�…

ニーブを無事に寄贈いたしました。
平成22年(2010)4月に完成した2作目のニー�…

民具作り教室 305回
完成!!!
やっと完成です。
何を入れたい…

民具づくり教室 304回
いよいよクージかごの全体像が見えてきまし…

民具作り教室 303回
「クージかご」に挑戦中
底部分のアジロ編�…

民具づくり教室
クージカゴの編始めは底の部分。
網代編の�…